GAME PCゲームで勝ち抜くための情報満載!
『OPUS 星歌の響き』インディーゲームを育てる「メタゲーム」としてのプレイヤー【インディーゲームレビュー 第113回】
近年すっかり一般的になったクリエイターとファンのコミュニケーション。そこにはSNSなどに留まらない、さまざまな交流が存在する。ゲームクリアのご褒美として、ボーナスコンテンツを盛り込んだ本作もまた、新しい取り組みを行っている。

『OPUS 星歌の響き』をクリア後、何の気なしに再プレイをして、驚かされた。メインメニューに「舞台裏」という項目が追加されていたからだ。そこには代表のブライアン・リー氏によるボイスメッセージ11本が収録されており、ゲームの解説やスタジオの近況、プレイヤーに対する謝辞などが「日本語と英語と中国語」で述べられていた。筆者は『OPUS』シリーズがリリースされる前年の2015年に台湾でリー氏をインタビューした経験があり、懐かしく思い出された。
アメリカ留学経験があるリー氏にとって英語は問題ないだろう。しかし台湾人であるリー氏にとって、日本語でのボイスメッセージは、容易ではなかったと推察される(少なくとも2015年のインタビュー時は、日本語は不得手だった)。にもかかわらず、ゲーム中でリー氏の日本語の発音は完璧だった。今回で3作目を数える『OPUS』シリーズは日本語ローカライズの品質でも知られており、月並みなファンサービスを越えて、日本のゲーマーと関係性を築いていこうという意思が感じられた。
本作に限らず、ゲーム開発者がゲームをメディアとしてとらえ、その中でプレイヤーに直接メッセージを発信する行為が、徐々に増加中だ。本連載でも過去に取り上げた『Forager』は好例だろう。従来、こうした制作者と消費者を繋ぐ役割はゲームメディアが担ってきた。近年ではSNSがその役割を代替している。そこに新たにゲーム自身が加わってきた。しかも本作では、クリア後の追加コンテンツとしてだ。ゲームをクリアするような濃いファンにとって、嬉しいサプライズだろう。
ライトノベルで書評家による「解説」ではなく、作者が執筆する「あとがき」が求められるように、ファンはクリエイターの価値観や趣味嗜好を含めてコンテンツを消費している。言い換えればクリエイター自身も商品になっているのだ。こうした行為は現代アート界では当たり前で、インディーゲームでも本作のように作家性の強いジャンルでは、一般的になっていくと思われる。本作は内容もさることながら、そうしたファンとのコミュニケーションを新しいスタイルで進めている点で評価できる。

もっとも、本作は「舞台裏」コンテンツがなければ、今ひとつ難解な内容で終わった印象もぬぐえない。風水と龍脈をベースにしたSF的な世界観が特殊なうえ、固有名詞が難解だからだ(中には「瀛海(えいかい)」「燭龍(しょくりゅう)」など、読み方がわからない単語もあった)。しかも本作は、ゲームを進めながら徐々に世界観を提示していくスタイルをとっている。自己中心的で感情移入しにくいキャラクターも多く、ゲームの序盤ではストレスに感じられる点もあった。
ただし、それぞれのキャラクターの過去や行動原理、そしてゲームの基本的な進め方がわかってくると、がぜん面白くなっていく。『機動戦士ガンダム』に代表される、1980年代のリアルロボットアニメにも似たスタイルだ。『FTL: Faster Than Light』にも似た宇宙探索に、ビジュアルノベル的なストーリー要素、キャラクターの魅力、ユニークな世界観など、さまざまな要素が混在しており、ボーイミーツガールの青春ものが好きなプレイヤーにはおすすめだろう。
本作の主要キャラクターは「没落貴族の青年リバク」、「恒星間レーダーの能力を持つ巫女のエイダ」、「エイダを姉と慕うエンジニアの少女ラムダ」の3名で、ゲーム全体が年老いたリバクの回想で進んでいく。これが優れた伏線になっていると共に、ゲームならではの「死に戻り」の説明にもなっており、感心させられた。たとえゲームオーバーになっても、「ここで死んでしまったら、今こうして生きているわけがない……もう一度、思い出してみよう(=再挑戦してみよう)」というわけだ。

ゲーム中にプレイヤーが行うことは、宇宙船「紅楼」を操って太陽系「山塊」を移動し、膨大なエネルギーが眠る小惑星「龍脈」を探索していくことだ。「龍脈」を探索するとアイテムが入手でき、換金すると「紅楼」が強化できる。これを繰り返しながらストーリーを進めていくというわけだ。また、星間上での龍脈探知にエイダ、龍脈上での現地探索をリバクが担当し、それぞれサウンドを用いた異なるギミックが組み込まれている。サウンドトラックも秀逸で、癒されること請け合いだ。
このように本作ではゲームシステムとストーリーの融合に対する配慮が秀逸で、『OPUS 地球計画』『OPUS 魂の架け橋』に続く、本シリーズの特徴にもなっている。ストーリー上のつながりは乏しいが、世界観がゆるやかにつながっており、「東洋的なフレーバーを持つSF的な世界観」「少年と少女のバディもの」「主人公がゲームを通して内面と向き合う」などの共通項がある。本連載でも過去にレビュー済みなので、参考にして欲しい。
『OPUS 地球計画』真のゲーム体験を提供するのは誰か【インディーゲームレビュー 第3回】
『OPUS 魂の架け橋』コンテキストが生み出す彼岸の物語【インディーゲームレビュー 第42回】
その上で本作ではグラフィックに3D CGが多用され、表現力が格段に向上した。その違いは過去作のスクリーンショットを見れば自明だろう。スタジオも4名から二十数名にまで成長したという。言うまでもなく、ファンあってのことだ。インディーゲームの支援には、ゲームを購入するだけでなく、プレイ動画を配信する、ブログやイラストを書く、SNSで投稿するなど、さまざまなやり方がある。ここではゲームの支援を通してシリーズを育てるというメタゲーム的な関係性がみられるのだ。
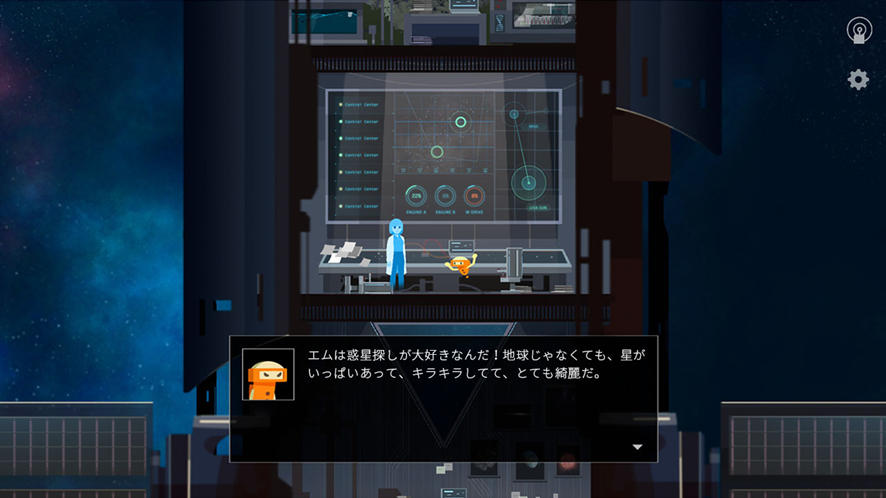 『OPUS 地球計画』
『OPUS 地球計画』
 『OPUS 魂の架け橋』
『OPUS 魂の架け橋』
 『OPUS 星歌の響き』
『OPUS 星歌の響き』
もっとも過去2作では雰囲気ゲームの要素が強かったのに対して、本作ではストーリー面が強化されている。その結果、ゲームの終盤でプレイヤーがゲーム世界から締め出されているようにも見える。
過去の連載で取り上げた例では『INMOST』に近いスタイルだ。そのうえで『INMOST』と同じく、「ハッピーエンドの呪い」からの脱却を試みている。この点については賛否両論があるだろう。個人的にも作り手側の意図は理解できたが、少々強引なようにも感じられた。
前述の通り本作には3名(+1名)の主要キャラクターが登場するが、中心となるのがリバクとエイダだ。リバクの行動指針は新しい龍脈を発見して、一族を復興させること。これに対してエイダは幻の龍脈「黒龍」を発見して、行方不明になった師匠に再会することを旅の目的にしている。ストーリーは7章構成で、ハリウッドの脚本術として知られる三幕構成をベースに進む。両者の望みはゲームを通して達成されるが、それでいて単純なハッピーエンドに終わらない点に本作の妙がある。
おそらく制作者は、ハリウッド的な「愛は宇宙を救う」結末ではリアリティに乏しいと考えたのではないだろうか。人間には時として、自分ではどうしようもない、大きな問題に翻弄されることがある。それでも、諦めずに進んでいれば、最後には道が開ける……。本作にはこうした、大河ドラマ的なメッセージが感じられる。そこに台湾そして大陸の文化が感じられる、といえばうがち過ぎかもしれないが、終盤に至る過程で、そうしたコンテキストが感じられた。
同じように日本では苦難に耐え忍ぶ物語に一定の需要がある。次から次に試練が襲いかかり、その過程で主人公が「自分だけの生き方や、小さな幸せ」をつかみ取る、というプロットだ。ポイントは主人公の心理や感情描写を重視し、事態の解決や課題の達成を軽視する点。昭和中期までの邦画に多く、「個人の努力で問題が解決し、幸せが訪れる」ことに現実感を得にくい時代が背景にあったと考えられる(※1)。同じように江戸時代に心中物が流行ったのも、身分制度と関係がある。

ただし、本作ではリバク、エイダ、ラムダ、年老いたリバクと、状況に応じてそれぞれの視点が入れ替わりながらゲームが進む。つまり物語的には三人称視点なのだが、キャラクターを操作しながら進める関係上、一人称視点の性格が紛れ込む。しかもゲームは小説と違って「地の文」がない。そのためゲームを遊びながら、しばしば自分が誰なのか、混乱におそわれた。このことは、特に強制イベントで問題の火種になる。「ゲームはプレイヤーの選択で進む」原則が阻害されるからだ。
この問題を防ぐには、主人公=プレイヤーキャラクターの視点を固定し、NPCを実質的な主役にする、などの手法が考えられる。近年の『ドラゴンクエスト』シリーズでは主人公にかわって、NPCがストーリーを牽引しているのは好例だ。一方で重要な選択については、主人公視点でプレイヤーに選ばせるのは、言うまでもない。本作ではこの視点がブレている上に、重要な決定にプレイヤーが関与できない点で、物足りなさが感じられた。
もっとも本作における評価は高く、この点を問題視するレビューは少ない。ゲームを実際にプレイするのではなく、実況プレイなどで「観て楽しむ」ユーザーからすれば、「ゲームはプレイヤーによる選択の連続で進む」という原則からして、ナンセンスだろう。ゲームのナラティブ(物語体験)演出については、いまだ確立した方法はなく、世界中で試行錯誤が続いている。今後も続くであろう、『OPUS』シリーズの挑戦に期待したい。
※1 沼田やすひろ『おもしろいストーリーをつくろう:画創り・インパクト・プロットで考えるストーリー構造論(仮説)マンガ・アニメ・ゲームのストーリー構築法 第三版:映像とストーリーの構造論』(沼books)参考
metacriticスコア:88
主な受賞歴:KOTAKU THE BEST VIDEO GAMES OF 2021、RPGFan EDITOR'S CHOICE、INDIE LIVE EXPO WINTER 2021 SHOWCASE 他
Steam『OPUS 星歌の響き』販売ページ
https://store.steampowered.com/app/1504500/OPUS/
SIGONO公式サイト
https://www.sigono.com/
『OPUS 星歌の響き』公式Twitterアカウント
https://twitter.com/sigonogames

クリア後に表示される制作者からのメッセージ
『OPUS 星歌の響き』をクリア後、何の気なしに再プレイをして、驚かされた。メインメニューに「舞台裏」という項目が追加されていたからだ。そこには代表のブライアン・リー氏によるボイスメッセージ11本が収録されており、ゲームの解説やスタジオの近況、プレイヤーに対する謝辞などが「日本語と英語と中国語」で述べられていた。筆者は『OPUS』シリーズがリリースされる前年の2015年に台湾でリー氏をインタビューした経験があり、懐かしく思い出された。
アメリカ留学経験があるリー氏にとって英語は問題ないだろう。しかし台湾人であるリー氏にとって、日本語でのボイスメッセージは、容易ではなかったと推察される(少なくとも2015年のインタビュー時は、日本語は不得手だった)。にもかかわらず、ゲーム中でリー氏の日本語の発音は完璧だった。今回で3作目を数える『OPUS』シリーズは日本語ローカライズの品質でも知られており、月並みなファンサービスを越えて、日本のゲーマーと関係性を築いていこうという意思が感じられた。
本作に限らず、ゲーム開発者がゲームをメディアとしてとらえ、その中でプレイヤーに直接メッセージを発信する行為が、徐々に増加中だ。本連載でも過去に取り上げた『Forager』は好例だろう。従来、こうした制作者と消費者を繋ぐ役割はゲームメディアが担ってきた。近年ではSNSがその役割を代替している。そこに新たにゲーム自身が加わってきた。しかも本作では、クリア後の追加コンテンツとしてだ。ゲームをクリアするような濃いファンにとって、嬉しいサプライズだろう。
ライトノベルで書評家による「解説」ではなく、作者が執筆する「あとがき」が求められるように、ファンはクリエイターの価値観や趣味嗜好を含めてコンテンツを消費している。言い換えればクリエイター自身も商品になっているのだ。こうした行為は現代アート界では当たり前で、インディーゲームでも本作のように作家性の強いジャンルでは、一般的になっていくと思われる。本作は内容もさることながら、そうしたファンとのコミュニケーションを新しいスタイルで進めている点で評価できる。

風水と「龍脈」をベースにした東洋的な世界観
もっとも、本作は「舞台裏」コンテンツがなければ、今ひとつ難解な内容で終わった印象もぬぐえない。風水と龍脈をベースにしたSF的な世界観が特殊なうえ、固有名詞が難解だからだ(中には「瀛海(えいかい)」「燭龍(しょくりゅう)」など、読み方がわからない単語もあった)。しかも本作は、ゲームを進めながら徐々に世界観を提示していくスタイルをとっている。自己中心的で感情移入しにくいキャラクターも多く、ゲームの序盤ではストレスに感じられる点もあった。
ただし、それぞれのキャラクターの過去や行動原理、そしてゲームの基本的な進め方がわかってくると、がぜん面白くなっていく。『機動戦士ガンダム』に代表される、1980年代のリアルロボットアニメにも似たスタイルだ。『FTL: Faster Than Light』にも似た宇宙探索に、ビジュアルノベル的なストーリー要素、キャラクターの魅力、ユニークな世界観など、さまざまな要素が混在しており、ボーイミーツガールの青春ものが好きなプレイヤーにはおすすめだろう。
本作の主要キャラクターは「没落貴族の青年リバク」、「恒星間レーダーの能力を持つ巫女のエイダ」、「エイダを姉と慕うエンジニアの少女ラムダ」の3名で、ゲーム全体が年老いたリバクの回想で進んでいく。これが優れた伏線になっていると共に、ゲームならではの「死に戻り」の説明にもなっており、感心させられた。たとえゲームオーバーになっても、「ここで死んでしまったら、今こうして生きているわけがない……もう一度、思い出してみよう(=再挑戦してみよう)」というわけだ。

ゲーム中にプレイヤーが行うことは、宇宙船「紅楼」を操って太陽系「山塊」を移動し、膨大なエネルギーが眠る小惑星「龍脈」を探索していくことだ。「龍脈」を探索するとアイテムが入手でき、換金すると「紅楼」が強化できる。これを繰り返しながらストーリーを進めていくというわけだ。また、星間上での龍脈探知にエイダ、龍脈上での現地探索をリバクが担当し、それぞれサウンドを用いた異なるギミックが組み込まれている。サウンドトラックも秀逸で、癒されること請け合いだ。
このように本作ではゲームシステムとストーリーの融合に対する配慮が秀逸で、『OPUS 地球計画』『OPUS 魂の架け橋』に続く、本シリーズの特徴にもなっている。ストーリー上のつながりは乏しいが、世界観がゆるやかにつながっており、「東洋的なフレーバーを持つSF的な世界観」「少年と少女のバディもの」「主人公がゲームを通して内面と向き合う」などの共通項がある。本連載でも過去にレビュー済みなので、参考にして欲しい。
『OPUS 地球計画』真のゲーム体験を提供するのは誰か【インディーゲームレビュー 第3回】
『OPUS 魂の架け橋』コンテキストが生み出す彼岸の物語【インディーゲームレビュー 第42回】
その上で本作ではグラフィックに3D CGが多用され、表現力が格段に向上した。その違いは過去作のスクリーンショットを見れば自明だろう。スタジオも4名から二十数名にまで成長したという。言うまでもなく、ファンあってのことだ。インディーゲームの支援には、ゲームを購入するだけでなく、プレイ動画を配信する、ブログやイラストを書く、SNSで投稿するなど、さまざまなやり方がある。ここではゲームの支援を通してシリーズを育てるというメタゲーム的な関係性がみられるのだ。
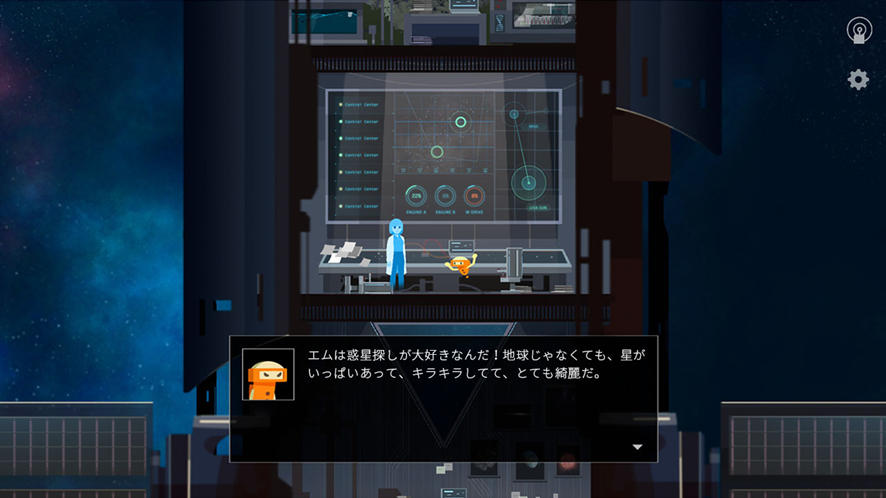 『OPUS 地球計画』
『OPUS 地球計画』 『OPUS 魂の架け橋』
『OPUS 魂の架け橋』 『OPUS 星歌の響き』
『OPUS 星歌の響き』そしてゲームのナラティブデザインに関する挑戦は続く
もっとも過去2作では雰囲気ゲームの要素が強かったのに対して、本作ではストーリー面が強化されている。その結果、ゲームの終盤でプレイヤーがゲーム世界から締め出されているようにも見える。
過去の連載で取り上げた例では『INMOST』に近いスタイルだ。そのうえで『INMOST』と同じく、「ハッピーエンドの呪い」からの脱却を試みている。この点については賛否両論があるだろう。個人的にも作り手側の意図は理解できたが、少々強引なようにも感じられた。
前述の通り本作には3名(+1名)の主要キャラクターが登場するが、中心となるのがリバクとエイダだ。リバクの行動指針は新しい龍脈を発見して、一族を復興させること。これに対してエイダは幻の龍脈「黒龍」を発見して、行方不明になった師匠に再会することを旅の目的にしている。ストーリーは7章構成で、ハリウッドの脚本術として知られる三幕構成をベースに進む。両者の望みはゲームを通して達成されるが、それでいて単純なハッピーエンドに終わらない点に本作の妙がある。
おそらく制作者は、ハリウッド的な「愛は宇宙を救う」結末ではリアリティに乏しいと考えたのではないだろうか。人間には時として、自分ではどうしようもない、大きな問題に翻弄されることがある。それでも、諦めずに進んでいれば、最後には道が開ける……。本作にはこうした、大河ドラマ的なメッセージが感じられる。そこに台湾そして大陸の文化が感じられる、といえばうがち過ぎかもしれないが、終盤に至る過程で、そうしたコンテキストが感じられた。
同じように日本では苦難に耐え忍ぶ物語に一定の需要がある。次から次に試練が襲いかかり、その過程で主人公が「自分だけの生き方や、小さな幸せ」をつかみ取る、というプロットだ。ポイントは主人公の心理や感情描写を重視し、事態の解決や課題の達成を軽視する点。昭和中期までの邦画に多く、「個人の努力で問題が解決し、幸せが訪れる」ことに現実感を得にくい時代が背景にあったと考えられる(※1)。同じように江戸時代に心中物が流行ったのも、身分制度と関係がある。

ただし、本作ではリバク、エイダ、ラムダ、年老いたリバクと、状況に応じてそれぞれの視点が入れ替わりながらゲームが進む。つまり物語的には三人称視点なのだが、キャラクターを操作しながら進める関係上、一人称視点の性格が紛れ込む。しかもゲームは小説と違って「地の文」がない。そのためゲームを遊びながら、しばしば自分が誰なのか、混乱におそわれた。このことは、特に強制イベントで問題の火種になる。「ゲームはプレイヤーの選択で進む」原則が阻害されるからだ。
この問題を防ぐには、主人公=プレイヤーキャラクターの視点を固定し、NPCを実質的な主役にする、などの手法が考えられる。近年の『ドラゴンクエスト』シリーズでは主人公にかわって、NPCがストーリーを牽引しているのは好例だ。一方で重要な選択については、主人公視点でプレイヤーに選ばせるのは、言うまでもない。本作ではこの視点がブレている上に、重要な決定にプレイヤーが関与できない点で、物足りなさが感じられた。
もっとも本作における評価は高く、この点を問題視するレビューは少ない。ゲームを実際にプレイするのではなく、実況プレイなどで「観て楽しむ」ユーザーからすれば、「ゲームはプレイヤーによる選択の連続で進む」という原則からして、ナンセンスだろう。ゲームのナラティブ(物語体験)演出については、いまだ確立した方法はなく、世界中で試行錯誤が続いている。今後も続くであろう、『OPUS』シリーズの挑戦に期待したい。
※1 沼田やすひろ『おもしろいストーリーをつくろう:画創り・インパクト・プロットで考えるストーリー構造論(仮説)マンガ・アニメ・ゲームのストーリー構築法 第三版:映像とストーリーの構造論』(沼books)参考
metacriticスコア:88
主な受賞歴:KOTAKU THE BEST VIDEO GAMES OF 2021、RPGFan EDITOR'S CHOICE、INDIE LIVE EXPO WINTER 2021 SHOWCASE 他
Steam『OPUS 星歌の響き』販売ページ
https://store.steampowered.com/app/1504500/OPUS/
SIGONO公式サイト
https://www.sigono.com/
『OPUS 星歌の響き』公式Twitterアカウント
https://twitter.com/sigonogames
【コラム】小野憲史のインディーゲームレビュー
- 『Loretta』絵画が与えたインスピレーションとゲームへの翻案【インディーゲームレビュー 第131回】
- 『Mecha Ritz: Steel Rondo』「難易度自動調整機能」がもたらす未来のゲーム体験【インディーゲームレビュー 第130回】
- 『IMMORTALITY』映像のジグソーパズル体験がもたらす映画とゲームの新しい可能性【インディーゲームレビュー 第129回】
- 『SIGNALIS』2Dからローファイ3Dへ~サバイバルホラーのリスペクトと再生【インディーゲームレビュー 第128回】
- 『Ukraine War Stories』ゲームの民主化とプロパガンダとしてのゲーム【インディーゲームレビュー 第127回】
- 『Stacklands』“インディーゲームのサブスク”という新しい開発スタイル【インディーゲームレビュー 第126回】
- 『迷路探偵ピエール:ラビリンス・シティ』絵本版とゲーム版、2つのピエールの違い【インディーゲームレビュー 第125回】
- ボタンを“離す”操作性がもたらすものとは? テナガザルの2Dアクション『Gibbon: Beyond the Trees』【インディーゲームレビュー 第124回】
- アクションとノベルのユニークな融合例『1f y0u're a gh0st ca11 me here!』にみる「アイデアのつくり方」【インディーゲームレビュー 第123回】
- 『ボクロボ ~Boxed Cell Robot Armies~』インディーゲームにおける「間口の広さと奥の深さ」問題【インディーゲームレビュー 第122回】
- 『Trek to Yomi』黒澤映画、そしてSAMURAIゲームとしての存在感【インディーゲームレビュー 第121回】
- 『A Musical Story』ゲームデザインと身体の関係性【インディーゲームレビュー 第120回】
- 『Vampire Survivors』が示すビデオゲームの歴史的文脈【インディーゲームレビュー 第119回】
- 『OMORI』に見るJRPGの再評価とインディーゲームならではの死と再生の物語【インディーゲームレビュー 第118回】
- 『Mini Motorways』カジュアルゲームのちょうどいい“難しさ”とは【インディーゲームレビュー 第117回】
- 『Small Life』アーティスト主導による新たなゲームデザインの可能性【インディーゲームレビュー 第116回】
- 『Unpacking』デベロッパー・プレイヤー・社会で変わるゲーム批評のあり方【インディーゲームレビュー 第115回】
- 『There Is No Game: Wrong Dimension』「ここにゲームはない」とはどういう意味なのか?【インディーゲームレビュー 第114回】
- 『OPUS 星歌の響き』インディーゲームを育てる「メタゲーム」としてのプレイヤー【インディーゲームレビュー 第113回】
- 『Assemble with Care』良質なインタラクティブ絵本ならではのスマホからの移植問題【インディーゲームレビュー 第112回】
- 『Twelve Minutes』ゲームならではの映画的サスペンス・スリラーは成功したか【インディーゲームレビュー 第111回】
- 【Please, Touch The Artwork】ゲームとアートをつなぐ「こんなの○○じゃない」の法則【インディーゲームレビュー 第110回】
- 『A YEAR OF SPRINGS』作者の思いを届けるためのゲームデザイン上の工夫【インディーゲームレビュー 第109回】
- 東京ゲームショウ2021オンラインにみる「ご当地ゲーム」の現状と可能性【インディーゲームレビュー 第108回】
- ゲームをとりまく差異がなくなっていく時代……「東京ゲームショウ2021 オンライン」に見る業界展望【インディーゲームレビュー 第107回】
- 『Genesis Noir』小説を脱構築したインタラクティブ・グラフィックノベルの可能性【インディーゲームレビュー 第106回】
- 『Say No! More』ゲームによる社会批評と「ノー」がもたらす全肯定【インディーゲームレビュー 第105回】
- 『Symphonia』フランスの学生チームが作ったゲーム版バンド・デシネ【インディーゲームレビュー 第104回】
- 『Dorfromantik』ドイツの学生チームが開発した癒やしの箱庭空間【インディーゲームレビュー 第103回】
- 『Haven』Co-opパートナーを迎えるためにデザインされたソロゲーム【インディーゲームレビュー 第102回】
- 『Arrog』ゲームの意味を解体するアートゲーム【インディーゲームレビュー 第101回】
- 『喰人記』富山のゲーム開発者コミュニティから生まれた新世代ノベルゲーム 【インディーゲームレビュー 第100回】
- 『The Magnificent Trufflepigs』ケーブルTV会社が問う、新たな文学表現としてのゲームの可能性【インディーゲームレビュー 第99回】
- 『Rytmos』に見る音楽パズルゲームの未来とメディアのあり方【インディーゲームレビュー 第98回】
- 『Hades』にみるゲームプレイとストーリーの関係性【インディーゲームレビュー 第97回】
- 『Ministry of Broadcast』操作性の悪さは何を物語るのか?【インディーゲームレビュー 第96回】
- 『Sea of Solitude』クリエイターが立てたコンセプトは達成されたか?【インディーゲームレビュー 第95回】
- 『Carto』ゲームとクリアとインディーゲーム【インディーゲームレビュー 第94回】
- 『Helltaker』解きたい人だけ解けばいいメタパズルゲーム【インディーゲームレビュー 第93回】
- 『Superliminal』個人制作から生まれるデジタルゲームならではのパズル体験【インディーゲームレビュー 第92回】
- 『Timelie』ゲームとパズル、それぞれのルールの違い【インディーゲームレビュー 第91回】
- 『天穂のサクナヒメ』本作のゲーム体験は架空の献立でも成立するか?【インディーゲームレビュー 第90回】
- 『Project Wingman』インディーゲーム開発者ならではの批評スタイル【インディーゲームレビュー 第89回】
- 大ヒットタイトルの登場とゲーム文化の成熟~インディーゲーム行く年来る年2020【インディーゲームレビュー 第88回】
- 『The White Door』現実世界に侵食する新感覚アドベンチャーゲーム【小野憲史のインディーゲームレビュー 第87回】
- 『TorqueL』インディーゲームの成熟と問われるゲームデザインのメリハリ【小野憲史のインディーゲームレビュー 第86回】
- 『アイザックの伝説 アフターバース』驚異のロングランを続ける伝説のインディーゲーム【インディーゲームレビュー 第85回】
- 『Untitled Goose Game ~いたずらガチョウがやって来た!~』予告動画とガチョウにまつわるコンテキストの違い【インディーゲームレビュー 第84回】
- 『Neon Beats』学生チームが作り出した音と映像の心地よい体験【インディーゲームレビュー 第83回】
- 『Mutazione』ゲームだからできるソープオペラ【インディーゲームレビュー 第82回】
- 『INMOST』が挑んだ「ハッピーエンドの呪い」からの脱却【インディーゲームレビュー 第81回】
- 『CARRION』ホラーゲームにおけるサウンドデザインとフォーリーの関係性【インディーゲームレビュー 第80回】
- 『FULFILLMENT』巨大配送センターとゲーミフィケーションの功罪【インディーゲームレビュー 第79回】
- 『Train Valley』『Train Valley 2』ファンの期待を受けた「正しい」進化のあり方とは?【インディーゲームレビュー 第78回】
- 『Beyond Blue』ゲームデザインは顧客のどのような課題を解決するのか【インディーゲームレビュー 第77回】
- 『Night in the Woods』におけるメッセージ性と、ゲームの三要素のゆらぎ【インディーゲームレビュー 第76回】
- 『A Short Hike』はなぜ英語圏ゲーム開発者の心をつかんだのか?【インディーゲームレビュー 第75回】
- 『公衆電話』プレイヤーと主人公の心情を近づける方法【インディーゲームレビュー 第74回】
- 『Besiege』動画共有サイト時代におけるゲーム開発のあり方【インディーゲームレビュー 第73回】
- ソーシャルゲーム市場からの転身は成功するか?『DIMENSION REIGN』がめざす新たな挑戦【インディーゲームレビュー 第72回】
- 新型コロナウイルスの感染拡大と『The Church in the Darkness』が示すもの【インディーゲームレビュー 第71回】
- 『Plague Inc: Evolved』新型コロナウイルス騒動が示す現実とゲームの関係性【インディーゲームレビュー 第70回】
- 現実のサインシステムをゲーム内にどのように組み込むか?『STATIONflow』の挑戦【インディーゲームレビュー 第69回】
- 『Ghone is gone』ゲーム開発の民主化が生んだ「不謹慎ゲーム」とクリエイターの倫理【インディーゲームレビュー 第68回】
- 『Mindustry』1+1が2にも3にも。アイデアの組み合わせで生まれるゲームデザイン【インディーゲームレビュー 第67回】
- 『Slay the Spire』ゲームならではのUI/UXがもたらす体験の向上【インディーゲームレビュー 第66回】
- 『Rebel Inc: Escalation』カジュアルな地域紛争解決ゲームに見る現実の抽象化と誇張化【インディーゲームレビュー 第65回】
- 『ロンリー・マウンテン・ダウンヒル』なぜ画面の下にむかって進むゲームは少ないのか?【インディーゲームレビュー 第64回】
- 『陶芸マスター』SNS時代が可能にした自己承認欲求とゲームの関係【インディーゲームレビュー 第63回】
- 『Rugby Champions』ゲームだから理解できるラグビーのリスクとリターンの本質【インディーゲームレビュー 第62回】
- 「TGS2019」インディーゲームコーナーで見つけた意欲作たち【インディーゲームレビュー 第61回】
- 連載60回記念! いま改めて遊んでみたい、ゲームの特殊性を感じさせる名作インディーゲーム3本【インディーゲームレビュー 第60回】
- 『HEADLINER』ゲームによる社会批評という新しい可能性【インディーゲームレビュー 第59回】
- 『Never Alone (Kisima Ingitchuna) 』ゲームが語り継ぐ少数民族の記憶【インディーゲームレビュー 第58回】
- 『Moonlighter』デジタル流通だからできるアップデートとコミュニティの相乗関係【インディーゲームレビュー 第57回】
- 『Baba Is You』多様なダイナミクスを生み出す優れたメカニクス【インディーゲームレビュー 第56回】
- 『WILL-素晴らしき世界-』が醸し出す等身大の中国ゲーム事情【インディーゲームレビュー 第55回】
- 『Lu Bu Maker』日韓で進むゲームデザインの相互交流【インディーゲームレビュー 第54回】
- 『Forager』大目標が消えた時代で生まれたコミュニティベースゲーム【インディーゲームレビュー 第53回】
- 『Academia : School Simulator』長所を伸ばし短所を減らす理想的な続編制作【インディーゲームレビュー 第52回】
- 『GRIS』美しくもはかない精神世界を旅するゲームと、多くのフォロワーが抱える課題【インディーゲームレビュー 第51回】
- 『Pikuniku(ピクニック)』にみるゲームと物語のユニークな関係性【インディーゲームレビュー 第50回】
- 『Into the Breach』にみるターン制ストラテジーの革新【インディーゲームレビュー 第49回】
- 『環願 Devotion』問題に見る現実とゲームの接続……ゲームはなぜ社会問題化するのか【インディーゲームレビュー 第48回】
- 『Opus Magnum』人はなぜ遊ぶのかを思い出させてくれる良質パズル【インディーゲームレビュー 第47回】
- 『Minit』ゲームジャム時代のインディーゲーム開発【インディーゲームレビュー 第46回】
- 『Semblance』南アフリカの新鋭パズルゲームは、なぜわかりにくいか【インディーゲームレビュー 第45回】
- 『Return of the Obra Dinn』AAAとインディーゲームを結ぶ難易度構造のループ【インディーゲームレビュー 第44回】
- 『Old School Musical』コントローラーとUIの関係性が生み出すリズムゲームの可能性【インディーゲームレビュー 第43回】
- 『OPUS 魂の架け橋』コンテキストが生み出す彼岸の物語【インディーゲームレビュー 第42回】
- 『Bad North』ミニマルなゲーム開発とミニマルなゲームデザイン【インディーゲームレビュー 第41回】
- 『Gorogoa』認知のフレームを軽やかに飛び越える絵画的パズルゲーム【インディーゲームレビュー 第40回】
- 『The Gardens Between』スマホゲーム会社ならではの操作デザインがもたらす、ユニークなゲーム体験【インディーゲームレビュー 第39回】
- 『Firewatch』が描くアメリカ版『ぼくのなつやすみ』が意味するもの【インディーゲームレビュー 第38回】
- 『To the Core』が示す、学生が学ぶべきゲーム開発スキルのトレンド【インディーゲームレビュー 第37回】
- 『DYO』に見るプレイヤー中心ゲームデザイン【インディーゲームレビュー 第36回】
- 『Life Goes On: Done to Death』インディーゲームが切り開くゲームデザインの彼岸【インディーゲームレビュー 第35回】
- 『State of Anarchy Master of Mayhem』ヘタウマが創り出すマイクロゲームの可能性【インディーゲームレビュー 第34回】
- 『アガルタ』ゲームエンジンから離れることで実現した世界との遊戯【インディーゲームレビュー 第33回】
- 『VA-11 Hall-A』ゲームが描き出す新しいホームドラマ【インディーゲームレビュー 第32回】
- 『Tooth and Tails』アメリカ人が作ったロシア革命のパロディRTS【インディーゲームレビュー 第31回】
- 『CHUCHEL』にみる“ゲーム”と“物語”の折衷点、そしてアドベンチャーゲーム【インディーゲームレビュー 第30回】
- 『タロティカ・ブードゥー』作ることと、それ以上に大切な伝えること【インディーゲームレビュー 第29回】
- 『エース・オブ・シーフード』にみる国産インディーゲームと日本らしさ【インディーゲームレビュー 第28回】
- 『OneShot』ゲーム制作における「守破離」を体現した作品に求められる、もう一つの「守破離」【インディーゲームレビュー 第27回】
- 『BomberCrew』なぜB-17ではなくランカスターなのか、「マジックナンバー7」の真の意味を十二分に生かしたゲーム【インディーゲームレビュー 第26回】
- 『RUINER』自由度の高い成長システムと、その果てにある究極の「ゲーム」像とは【インディーゲームレビュー 第25回】
- 『Shadow Tactics: Blades of the Shogun』静と動のリズムによって演出されるゲーム体験【インディーゲームレビュー 第24回】
- 『リトルナイトメア』現世代機だから可能になった光と影のパズル【インディーゲームレビュー 第23回】
- 『Prison Architect』刑務所シムに見る民活刑務所の今〜ゲームはヒット、現実は?【インディーゲームレビュー 第22回】
- 『返校』台湾の白色テロを扱った異色作における演劇的な視覚演出【インディーゲームレビュー 第21回】
- 『UNDERTALE』個人制作に近づくインディーゲームの魅力を伝える上で重要なこと【インディーゲームレビュー 第20回】
- 『CUPHEAD』ハイクオリティ個性派アクションシューターは本当に個性的なのか?【インディーゲームレビュー 第19回】
- 『Old Man’s Journey』映画とゲーム、似て非なるメディアが示す作劇法の違い【インディーゲームレビュー 第18回】
- 『フィンチ家の奇妙な屋敷でおきたこと』登場人物の死を積み重ねて生を描く【インディーゲームレビュー 第17回】
- 『RiME』その主人公はいったい誰なのか? ゲームとプレイヤーの関係性に迫る【インディーゲームレビュー 第16回】
- 『This War of Mine』ゲームはついに戦時下の生活を描いた【インディーゲームレビュー 第15回】
- 『911 Operator』ストレスループでつながる現実社会とゲーム【インディーゲームレビュー 第14回】
- 『Brothers: A Tale of Two Sons』1つのコントローラーで兄弟を操作、ゲームならではの物語体験【インディーゲームレビュー 第13回】
- 『スキタイのムスメ』にみるストレスと開放のループ構造、そしてパズルのセンス【インディーゲームレビュー 第12回】
- 『Expand』ゲームの基本形が見せたセンスオブワンダー【インディーゲームレビュー 第11回】
- 『FTL: Faster Than Light』における「発掘的デザイン」の意味【インディーゲームレビュー 第10回】
- 『Thumper』光と音が暴力的にうずまくゲームにコンティニューボタンが存在しない理由【インディーゲームレビュー 第9回】
- 『Beholder』が持つコンテキストの重要性〜ロシアでしか作れない怪作【インディーゲームレビュー 第8回】
- 『GoNNER』2Dプラットフォームシューターでオーディオ体験が評価された理由【インディーゲームレビュー 第7回】
- 『ABZÛ』画面の一部が常に揺れ動く世界での探索【インディーゲームレビュー 第6回】
- 『Hyper Light Drifter』ユーザーをグループに分類し、それぞれに適した施策を提供する……【インディーゲームレビュー 第5回】
- 『Rusty Lake: Roots』海外TVドラマからヒントを得たアドベンチャーゲーム【インディーゲームレビュー 第4回】
- 『OPUS 地球計画』真のゲーム体験を提供するのは誰か【インディーゲームレビュー 第3回】
- 『Her Story』今や絶滅危惧種となった「コンストラクションゲーム」の正統進化【インディーゲームレビュー 第2回】
- 『INSIDE』少年は逃げる、でもどこに向かって……?【インディーゲームレビュー 第1回】


